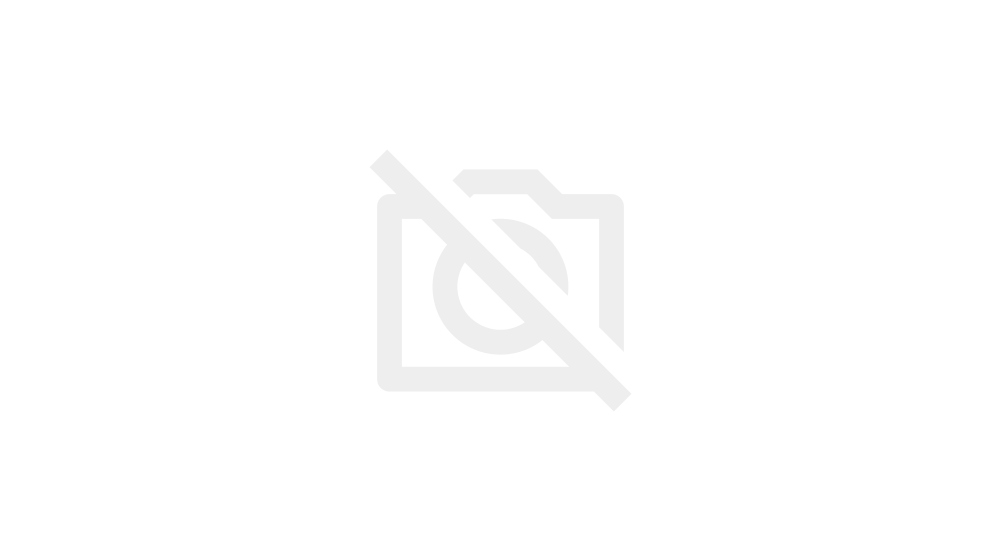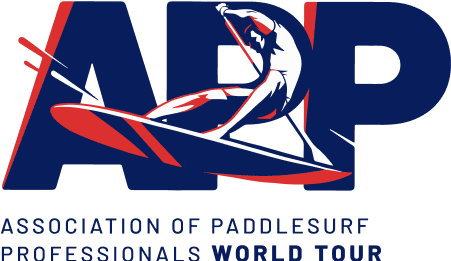このページをご覧の方は、SUP(サップ)が『Stand Up Paddle board』の略であることはご存じだと思いますが、その成り立ちまで知っていますか?
このページではサーフィンによく似ているようで全く違う、近年人気のSUPについて、初心者向け解説ページ『ヨガだけじゃない!SUP(サップ)の始め方ガイド』で書ききれなかったSUPの基本情報について、徹底解説していきます。
SUPの成り立ち
SUPのボードは、どことなくサーフボードに似ていますよね。
それもそのはず、SUPはハワイのサーフィン文化から派生したと言われており、平たく言うとサーフィンの親戚みたいなものです。
因みに、サーフィン自体の起源ははっきりしていませんが、ハワイ諸島の古代ポリネシア人が行っていたものが原型とされています。
有名なカメハメハ大王もサーフィンを嗜んでいたと言われていますが、道具や安全対策が発達した現代でも怪我や事故と隣り合わせのサーフィンですから、古代文明でもそれなりに危険な遊びだったことでしょう。
SUPはそんな頃、サーフィンを行う人達の安全を見守るために始まったと言われており、カヌーのパドルを流用していたようです。
陸の高台の方が見守りやすいでしょうが、何かあった際にすぐに駆け付ける海上にいられるということと、船よりも小回りが利くということが用途として向いていたのだと思います。さながら現代でいうところのライフセーバーのようなものだったのでしょう。
現代でもライフセービングではボードを使った競技があるので(パドルは使わないが)、ルーツは近そうです。
その後もサーフィン文化の片隅で、ボードとパドルを使った遊びとして続いていたことと考えられますが、サーフィン程の伝統文化としては捉えられていなかったからか、あくまでも遊びの域を出ていなかったのでしょう。特段フィーチャーされることもなく、サーフィン文化の日陰になるようにして歴史の中では目立った情報が残っていません。
1960年代のSUP黎明期
宣教師によりヨーロッパの文化や宗教の布教の妨げになるとされ、ボードを燃やされるなどし途絶えていたサーフィン文化ですが、20世紀初頭になり再興する動きが出てきます。
この頃のハワイには、元々住んでいたハワイアンだけでなく多くの移民がいたため、そうした人々も含めてサーフィンを楽しむようになります。それだけ波に乗る行為が楽しかったんですね。
1960年代になると、一般的なサーフボードが復活し、日本でも駐留アメリカ人を通じてサーフィンが普及されるなど、急速に世界中でサーフィン人気が高まります。※こうしたサーフィン文化については「一般社団法人日本サーフィン連盟」のページが詳しいので、気になる方はそちらをご覧ください
さて、こうして世界中で人気となったサーフィンですが、本場ハワイではどうなっていたでしょう?
場所は広大な砂浜でハワイでも屈指の人気を誇るワイキキ・ビーチ。ハワイに行ったことがない方でも聞いたことない人はいないんじゃないかと思うくらい有名ですよね。
当時ここでは、アウトリガーカヌーという船に観光客を乗せるためビーチボーイが働いていました。一般的にアウトリガーカヌーは、普通のカヌーと違い、アウトリガーという浮きで支えられている側だけ漕げばいいので、ダブルブレードのカヌーパドル(両側に漕ぐ面があるパドル)ではなく、シングルブレードのパドルを用います。
ビーチボーイ達は、遊びでこのアウトリガー用のパドルを使いロングボードで波乗りを楽しんでいたそうです。これが現代SUPの幕開けと言えるかもしれません。
因みに、この独特のサーフスタイルは『ビーチボーイスタイル』と呼ばれ、現代でも専用ボードが販売される程愛好者がいます。
こうして見ると、やはりSUPはサーフィンなんだなと実感しますね。
2000年代からのSUP人気爆発
ビーチボーイスタイルでパドルを使ってボードを乗りこなすことが人気となりましたが、その後、ショートボードなどの純粋なサーフィン人気が過熱し、SUPのような遊びは世間的に忘れられてしまいます。
そんなサーフィン人気の中で、ビックウェーバーという驚異的な大波に挑む命知らずのサーファーが誕生してきます。
大波に挑むことは並大抵のことではありません。道具や技術体系の進歩ももちろんありました。しかし古代のサーフィンと違い、彼らはセンスだけでなく、トレーニングを積むことで大波に挑むことができたのだと思います。そのトレーニングの一つがSUPでした。
サーフィンの練習なら波に乗ればよいと思うかもしれませんが、仕事や家庭の合間にそう都合よくトレーニングに向いた波があるとは限りません。場合によっては波がないときだってあるでしょう。これでは効率的にトレーニングできないので、彼らは波のないときにできるトレーニングとしてSUPを行い、波に乗るための体幹やバランスを鍛えたのです。
そうして、伝説的ビックウェーバーとして、レアード・ハミルトンやデイヴ・カラマが知られるようになってきます。ちなみに2名とも存命で、デイヴ・カラマは現在SUP競技者としても有名です。

その頃が2000年代前後で、それまでは「波のある場所で楽しむサーフィン」や「風のある場所で楽しむウインドサーフィン」が広く知られていましたが、これでは良い波や風がない場所では当然楽しめなかったところだったので、水面を選ばず楽しむことができるSUPは一気に人気を得て、今では全世界で100万人の愛好者がいると言われる程に広がりを見せています。
2010年以降のSUP
爆発的な広がりを見せるSUPムーブメントの中でしたが、今まではあくまでサーフィン文化の延長にあるような感じでした。しかし2010年頃からSUP界が新たな方向性を見せていきます。
サーフィンの国際統括団体である「ISA(国際サーフィン協会)」がSUPでも国際統括団体となり、2012年から世界大会を開催したりインストラクターやコーチの養成、イベントの実施など、草の根活動から競技レベルまで幅広い発展に力を注ぎ始めました。因みにSUPの国際団体としてはCAS(国際カヌー連盟)がありましたが、スポーツ仲裁裁判所によりISAが統括団体に決定しています。これほど争うということは、暗にSUPというカテゴリーの将来性が高いことの証左だと思います。
世界大会は、コロナ禍で中止になるまでにペルー、ニカラグア、メキシコ、フィジー、デンマーク、中国、エルサルバドルなど、世界中で行われており、文字通り水面を選ばないSUPの利点が最大限に生かされています。
また、国際プロ競技団体としてAPPがあり、そちらの世界大会では、大阪の淀川で行われたものもあります。この大阪大会は2022年に再度行われるとのことなので、世界のSUPプロを間近で見るチャンスですね。
このように、2010年以降はプロ競技と、またそのグラスルーツという両面で公的に後押しを受けて育ってきたコンテンツと言えます。
そのため、プロが使うボードの外にも、様々な用途のボードが生まれてきており、SUPの楽しみ方の細分化が進んできてもいます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
SUPはサーフィンをルーツとするスポーツであることは確かですが、徐々にそこから独立しそうな勢いをつけていることが分かっていただけたんじゃないかと思います。
『水面があればどこでも楽しめる』『怪我のリスクが少ない』という始めやすく、続けやすいSUPの利点は今後最大化され、子供たちの遊びからプロ競技を経て、生涯スポーツとしてさらに広まっていくものと思います。
そのため、何となく感じるサーファーの少し近づきにくい感じとはまた違った空気感をSUP文化からは感じるので、もう少し万人受けするようなスポーツになるかもしれません。
とはいえ、ウォータースポーツとしての危険性は変わらないため、何も知らない状態で勢いだけで始めると事故にあう可能性もあります。
しっかりとリスク管理をしつつ安全第一で、目いっぱい楽しみましょう!